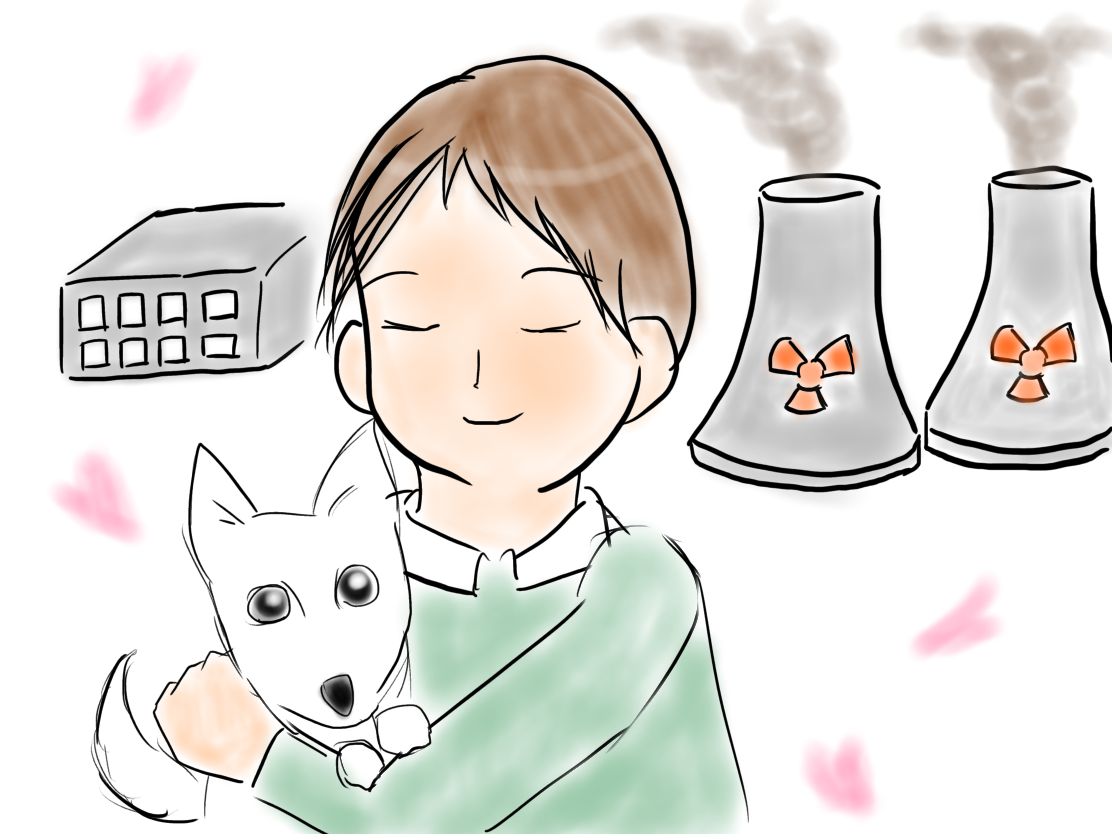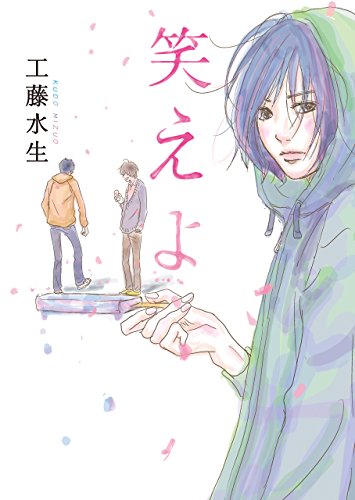今さら感がありますが、昨年下半期の「読んで良かった本」ランキングです。
今回はジャンルごちゃ混ぜ、20位から紹介したいと思います。
20位 すべてのものは優しさをもつ
神保町ブックフェスタの、ナナロク社のブースで見つけて買った短歌集です。
風景や抽象的な表現などはあまりなくて、自身の身体と、コミュニケーションについての歌が多い歌集でした。
そしてナナロク社の本は、挟み込みの愛読者カードのデザインセンスが良いなぁ、と毎回感じます。
19位 アルケミスト
ずいぶん前に、某オンライン書店でのプレゼント企画でこの本を手に入れていました。童話のような物語で、終わり方もロマンチック。個人的には、石が好きなのでクリスタルが出てくるところに惹かれました。
18位 嫌われ女子50
今から約12年前の本になります。「モテ」系の格好が「白ワンピに巻き髪」みたいなところに時代を感じます。
こんな人さすがにいないよ〜と思いながら読み進めたものの、「職場で嫌われる女子」の章は、割と実用的なマナー本っぽいと思いました。
そしてこのテの本、合間のコラムが結構面白いんですよね。この時代だと「性差を考慮した上でどう振る舞うか」という視点が多くて、そこから深いところまで刺せているような感じがあります。
「おしゃP」も、少年アヤちゃんも、もはや懐かしい。「ブス活動」「オカマコラムニスト」みたいな表現にも時代を感じました。
17位 魔王
ずいぶん長期間積読していた本ですが、2024年に読むことはそれはそれで正解でした。衆議院の解散、カリスマ性のある政治家、首相への襲撃など、昨今の話題と重ね合わせてしまいました。
解説では「00年代の政治を予見していた」とありましたが、いや、2020年代にも通じてるよ、と思ったり。伊坂幸太郎作品は「死神」シリーズも読んでいたのでニヤリとできる部分もあったものの、嫌な展開を想像しながら読み進めてしまう部分も。
二人の兄弟が主人公ですが、このような「兄弟」の人生展開としては、同じ著者の『フーガはユーガ (実業之日本社文庫)』を思い出す部分もありました(というか『魔王』のほうが先か)。なんというか、作者の「死」への考え方も、必ずしもネガティブなものではないように感じて、これらの終わり方をどう捉えるかに読み手の個性も現れるよなぁ、なんてことを思いました。
16位 この夏のこともどうせ忘れる
数年前に誰かがブログか何かでこの本を紹介していたのを見て、短編集好きな私は気になり、買ったような気がします。
「同性愛っぽい作品」みたいな文脈で紹介していたものだったかな? 夏休みの高校生たちの、爽やかでもない恋愛とも友情ともなんとも形容し難い関係を描いていて、世界観としては嫌いじゃありません。
人間の描写がちょっと記号的な感じもあるけど、そこは主人公たちや作者の「若々しさ」と表裏一体な感じもしました。余韻を残すつもりだったのかもしれないけど、伏線があまりにもほったらかしのような印象を受けた作品があり、ちょっと惜しい印象を受けます。
私は短編集ではだいたい「お気に入り」の作品を決めることが多いのですが、どれもそれぞれ惜しい感じで、好きな作品がなかなか決められませんでした。あえて挙げるなら、夏の山の中で、友達たちとどんどん会えなくなっていく少年の話が一番、印象に残っています。
15位 「日本」ってどんな国?
本文中での主張そのものは妥当なところが多いとは思うものの、このタイトルは合っていないように思えました。フラットに感じられないというか、結論ありきでの引用に思えて、「日本」と称するにはだいぶ限られた側面にも思えます。
例えば、日本の医療や衛生に関しての質の高さや諸問題についても触れてほしい、と思ってしまいました。
また、本文中で紹介されている「ジョブ型雇用」に関しては私は期待しているものの、一方で、その部分だけいじっても成立しにくい気もするので、そこまで踏み込まないのは本としては物足りなく思えました。
余談ですが、本文中で協力者として名前が出ている鈴木翔さんは『教室内(スクール)カースト (光文社新書 616)』の人かな、と懐かしくなりました。
14位 哲学のはじまり
ここ半年くらいよく参加している「双子のライオン堂」人文読書会での課題図書になったので読んでみました。
この「学びのきほん」シリーズは薄くて読みやすく、忙しい人でも短時間で読了しやすいので、社会人多めの読書会の課題図書にもまさにピッタリ。
この本の読書会では、哲学者たちの派閥の話や「スピノザは明るくて好き」という話をする人がいたり、私は「イデアの考え方って転生モノっぽい」なんて話をしました。
余談ですが、著者の戸谷さんは年齢も近く、現在は私の出身大学で勤務されており、共通の友人も多く、昨年は私の勤め先の会社で出している雑誌にもインタビューが掲載されたことがあるため、縁を感じている方です。
13位 自分とか、ないから。
本を出している友人知人はそこそこいるのですが、ここまでブレイクした人は初めてかもしれません。
ちなみに、これまで、私の友人知人で商業出版をした人のうち、最もブレイクしたのは『千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話』の著者の済東鉄腸さんだったのですが、彼を超えた気がしますね。
私は仕事柄、全国の書店を回ることがありますが、地方の書店でもこの『自分とか、ないから。』が平積みにされていたりポップが飾られていたりすると「すごいなぁ……」と改めて感じます。
また、私が以前勤めていた職場の同僚がこの本を「面白かった本」として紹介していたのを見たときは、ちょっとテンション上がりました。
著者は、もう何年も会っていない昔の知人(それでも何度かメッセンジャーでやり取りした形跡は残っていました)。2024年のサイン会で数年ぶりに再会して「懐かしい!」と言ってもらえて嬉しかったな。いろいろ活動していて「すごい人」だと思っていましたが、実際はかなり苦戦していたということが分かり、親近感を抱く部分もありました。個人的には、著者の「チームワークでの挫折」の話にすごく親近感が湧きました。本筋とはあまり関係ない部分ですが(笑)。
正直に言うと、ここまでこの本が売れたのは正直かなり「意外」です。「面白い。売れるのは当然だよね」という感想ではなく、「意外」なのが正直なところです。
とても読みやすくて、バズった面白ブログを読むようにスルスル読めたけど、もう少し歯応えがあるほうが私好みだったかも……というのが本音です(この本も人文読書会の課題図書にしてもらったら、同じような感想の人がいて心強かった)。
監修に専門家もついているのだから、1章ごとに解説があってもいいのでは……とも思いましたが、「そういうのを挟んだらこの本のノリが消えてしまうかもな」という気もします。
12位 作家の人たち
倉知淳作品は好きで割と読んでいますが、この著者にしてはイマイチだったかなー、というのが最初の印象です。ただ、いろんな作風の作品が入っていて、そういう意味では飽きずに楽しめました。
私も出版社勤務で、編集業の友人も多いので親近感を抱く部分もありました。各社のパロディにもニヤリとできたり。年収の話はリアル。選考会の話も楽しめました。
作中に出てくるラノベのタイトルが微妙にダサいのも、味わいが合って好きです(この著者は他作品でもそういう「ちょっとダサい」要素を感じるところがあるのですが、私は好きなタイプのダサさです)。
物語として収まりがいいのは「本の悪魔」の話で、子ども向けの怖い話にありそうだなと思いました。そして、著者はやっぱり猫が好きなんだな、ということを実感。
最後の話は切ないけど、その後どうなるか、読者の想像の余地があるのもまた「物語」を突き詰めた感じがして、ある種の皮肉もあり、ある種の面白さを感じました。
11位 本当は怖い動物の子育て
著者に関して賛否両論あるようですが、この本は普通に読み物として面白かったです。
タイトルはやや扇状的で「動物」とあるものの、いわゆる「動物」に限らず扱う対象は広く、虫や人間の行動や文化の風習についても解説されています。
動物の話も面白いですが、個人的には特に後半の、人間についての内容に興味深いものが多かったです。
中国の母系集団の民族のエピソードは、少子化対策にはとても良いだろうけど、いざ襲撃されたら弱いから一長一短あるよなぁ、と感じたり。アマゾンの部族の、産まれた子を育てるかどうかの選択を、現代日本では行われないようなやり方で母親に委ねるエピソードには衝撃を受けつつ、これはこれで「誰も悪者にしないやり方」にも思えたり、色々と心を動かされる内容でした。読後感は決して悪くない一冊です。
10位 客観性の落とし穴
こちらも、先ほど紹介した『「日本」ってどんな国?』と同様に、タイトルと中身にややズレを感じてしまいました。プリマー新書は良くも悪くもそういう本が多い印象があります。
作中で紹介されているドキュメンタリー映画「さとにきたらええやん」は以前、SNSで誰かが紹介してるのを見た覚えがあったので、この本に出てきたのには驚きました。その舞台について知れたのは意外な収穫でした。
この本では、優生思想的な考えに共感する人について、著者は「国家権力の内面化」のように言っていますが、障害のある人を「世話をする立場」として言ってる人も多いのでは……と思ってしまい、そのあたりが少々気になりました。
「他者を研究しつつ尊重するための条件」のくだりは、フィールドワークでも役立ちそうな考え方。というかこの本は、「アウトリーチ」や「フィールドワーク」の側面をもっと打ち出しても良かったのでは、と思えました。
9位 世界がわかる資源の話
エネルギー関係の仕事に転職したので、エネルギーについて学べそうな初心者向けの本を探していた矢先に見つけました。
薄めの本で読みやすい内容ではあったものの、電気代の高騰やウクライナ侵攻、活動家をめぐるあれこれなど、さまざまな分野に言及していて、内容は読み応えがありました。
いわゆる「エネルギー」に直接関わる内容というより、資源をめぐる政治にまつわる内容の本、という感じでした。求めていたものとは少し違いましたが、読めてよかったと思えた一冊です。
8位 ポエトリー・ドッグス
読書会の課題図書になったので読んでみました。「アートに関する本を読んでみたい」「詩を扱った本を読んでみたい」という流れからこの本に決まったような。
「いぬのマスターがいる不思議なバーでは、お酒と一緒に、詩を出してくれる」という世界観の物語。1話ごとにそれぞれ詩が紹介されています。文芸雑誌で連載されていたもののようで、1話が短く、気軽に読みやすい本です。
ちょうど、この本を読んでいた時期、SNSで「編集者は詩を直せるのか問題」が話題になっていたりもして、そういう意味でもタイムリーな読書となりました。
作中で紹介されている詩では、女性の生きづらさを描いた(と思えた)ものもあり、そういった作品が個人的には一番好きでした。
読書会では「詩は歴史的にどういう読まれ方をしてきたか」とか「この犬って、主人公にとってどういう存在なんだろう?」とか「自分の妄想を語るのと自分の実体験を語るの、どっちが恥ずかしい?」という話になったり、思わぬ方向に話題が広がり、盛り上がりを見せました。
7位 「ストーカー」は何を考えているか
知っている内容が多いかと思いきや、そんなことはありませんでした。
逗子ストーカー殺人事件の被害者の方、この本の著者に相談されていたとは……。
西海市のストーカー殺人のことも、関係していた県が3県にわたっており、連携不足だったことでこのような結果になってしまったということまでは知りませんでした。
また、カウンセリング中の振る舞い方の男女の違いのくだりや「お金と愛は共存できない」エピソードも、人間心理として興味深く読みました。
また、桶川ストーカー殺人において著者が被害者に対して失礼なことを書いてしまった件について、(その記事は私は知らないけど)この本の中で謝罪があることには好感が持てました。
個人的には、不倫からのストーカーの事例の場合は、被害者にも同情しにくいなぁ……なんてことも思ってしまいました。
6位 笑えよ
作者名が知人のペンネームと似ていること、私と同年生まれということが気になり購入したものの、長年積読していた小説。平易で飾り気のない筆致で面白く読めました。
タイトルは、最後まで読んで「なるほど、そういう意味か」という感想。恋愛というより奇妙な友情という感じで、「性の多様性」とは別のところで、「好き」のカタチは色々だよなぁと思う部分もありました。
10年以上前の本なので、同性愛についての描かれ方の、昨今との違いのようなものにも目が止まりました。そして表紙にいるのは3人のうちそれぞれ誰なのか想像の余地がある感じも良いし、作者名といい主人公といい、名前がやや中性的なのも好きです。
雪の描写の細かさから、さすが北大出身の作家さんだなぁと感じるところもありました。
北海道や東北出身で思春期の女子の心理描写の上手さといえば、加藤千恵や辻村深月作品を思い出すところですが、彼女たちの作風だとほんのりとセックスの要素が入ってきそうだよなぁと思ったり。この作品は、どこかやや「リアリティ」に欠ける感じのプラトニックさがあり、それがまた作者の瑞々しさ、フレッシュな感じを表していた気がします。
5位 絶望に効くクスリ 14
著者が、さまざまな著名人にインタビューをしたコミックエッセイ。こちらの本も、長年積読しててようやく読みました。
確か買ったのは2008年頃で、当時は山田真哉(『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?~身近な疑問からはじめる会計学~ (光文社新書)』が話題になった公認会計士)、山下洋輔(ジャズピアニスト)目当てで買いましたが、いざ読んでみて一番印象深かったのは、80代の女性の旅人・金井重さんのくだり。
特に最後のセリフは、彼女の生きた時代の「女性」のあり方が凝縮されている気がして、どこかギョッとさせられてしまいました。そして今はもうそんな時代じゃないことに対して、先人に感謝したくなりました。
金井さんは、この本での取材時点で80歳だったそうなので、今はお元気なのかな……と思わず検索してしまいました。
山田さんの著書もブーム当時読んでいましたが、考え方がユニークでやっぱり好きです。「未来バンク」の田中優さんは、社会起業やプロボノの先駆けという感じだな、と思えました。
長年積読してしまった本ですが、昨年のタイミングで読めてよかったな、と思えた一冊でした。
4位 ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた
こちらも、読書会の課題図書になったので読んでみた本です。
コロナの時期に、大学教授が、社会問題となっている現場に実際に訪れてみたり、実際にさまざまなことを試したり……そのような経験を描いたエッセイ集となっています。
タイトルの元になったのはおそらく『アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した~潜入・最低賃金労働の現場~ (光文社未来ライブラリー)』でしょう。元ネタの本も気になっていたこともあり、この斎藤さんの本も読んでみましたが、卑近な話題も多いエッセイ集なので読みやすかったです。
一定期間「プラスチック製品を含むものは買わない」というルールを課してはいたものの「買ってはいない、もらったものなのでセーフ」という認定をしていたりとか、自身に厳格すぎないところに親しみを感じました。
また、アイヌに関しては、同時期に展示を見たり本を読む機会があったのでそこは私も考えさせられたり、水俣に移住している友人もいるので「自分ももう一人のチッソ」という言葉も印象に残りました。
性教育やメンズメイクについても載っており、このような話題について男性目線での考えを知れたことには、心強さを覚えた部分もありました。
なんというか、それだけで決まるものでもないとはいえ、机上であれこれ述べるだけでなく、実際に身体を張って経験している人の言葉は、そうでない人よりは耳を傾ける価値があるな、と感じますね。経験することの大切さや研究者の暴力性など、さまざまなところに思考を巡らせることになる一冊でした。
3位 終わっていない、逃れられない
著者は10年来の友人です。一緒に福島県にも行き、被災地での資料収集に同行したりもした仲で、異性の親友というものがいるとすれば加島くんのような存在だろうな、と思うレベル。
2024年に私はエネルギーに関する出版社に転職し、北陸電力関係企業を訪問する富山出張の際、仕事終わりに加島くんにも会いに行きました。
新幹線の中でもこの本を読みましたが、原発をめぐる憤りについては耳が痛い部分もあったり。また、本書で紹介されてる作品には「ミクシィ」が出てきたところにも時代を感じました。
中学生の作品に対して「読み」を誘導しようとする姿勢への批判は痛快で腑に落ちます。震災文学に限らない、文芸批評としても読み応えがある本でした。
作中で紹介されている短歌集『Midnight Sun 新鋭短歌シリーズ』は私も読んでいましたが、正直、震災の作品を覚えていないのが悔やまれます。作中に出てくる岡井隆の歌集も気になっていたものの、震災の作品の本だったとは知りませんでした。読む機会があったら、その点にも目を向けて読んでみようかな。そんなふうに、読書の幅も広がりそうな一冊でした。
2位 ネガディヴ・ケイパビリティで生きる
こちらも読書会の課題図書だった本。少し厚めですが、3人での対話形式なので意外と読みやすい本です。
「即時に結論を出さずに、簡単に解決したり納得しない能力」を意味する「ネガティヴ・ケイパビリティ」という考え方。この技術を身につけるための本ではなく、3人が「問題とどのように向き合い続けていくか」を語り、さまざまな話題に発展していく対話集です。執筆陣のことを知らなくても楽しめると思います。
個人的には、「陰謀論」についてのくだりが印象に残りました。
読書会では「会話の様子に、関西の人っぽさを感じた」という意見がありましたが、確かに、京大界隈はそれはそれで独特の文化があったよなぁ、と思ったり、ジャンカラなど関西に多いカラオケチェーンの名前が出てきたのには、かつて京都で大学生だった私も、ちょっと懐かしくなる部分もありました。
……しかしこの本もまた、タイトルがあまり合っていないような気もしました。「SNSの倫理」みたいなほうがよかったのでは、多くの人に手に取ってもらえたのでは………という気持ちになったり。まぁ、もしかしたらこのタイトルにしたことで、あえて「届ける人を限定する」「売れすぎないようにする」ことに意味があったのかな、という気もしました。大手出版社ならこのタイトルにはしなかったかもしれないな、なんてことも思いました。
1位 教養としての犬
丸の内の丸善でエネルギー関係の本を見ていたとき、向かい側の棚が生き物に関する本で、偶然この本を知りました。買ってみたらあまりにも面白くて一気読み。イヌと人の歴史という文化的な部分にも、オオカミとの生物学的な違いや遺伝など科学的な部分にもどちらにも触れていて、タイトル通り「犬にまつわる教養」を幅広く知れた本でした。
本の中にある犬のイラストも、ほどよくリアルな優しいタッチでとてもかわいい。大人だけでなく、子どもが読んでも楽しめると思います。思ってた以上にイヌは頭もよく人の言動を理解していることがわかり、すごいなぁと思ったものの、怒られたときのバツの悪そうな顔についての解説が意外で、イヌと人の違いを痛感させられました。また、犬のミイラのくだりも印象深かったです。
ちなみに『教養としての猫 思わず人に話したくなる猫知識151』という本も出ていたので、こちらも買ってみました。