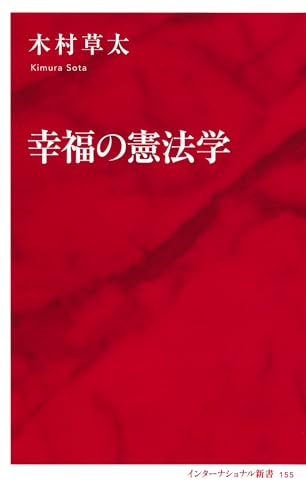読んで良かった本ランキング、今回も書こうと思います。
今回は、小説や漫画など、創作作品以外の書籍編です。
16位 書物と貨幣の五千年史
昨年お亡くなりになった書評家・永田希さんの本。
永田さんとは、じつはかなり前から各種SNSで相互フォローだったり「友だち」で、読書会的なイベントにもよくお誘いいただいていたのですが、なんだかんだ、結局一度も直接お会いすることはありませんでした。
この本は電子書籍で買って「積読」していたものの、訃報を機に読んでみました。
思ったより淡々としていて難解だった、というのが正直な感想です。ただ、レジュメを作って読むような読書会とは相性がいいかもしれないな、と思いました。
ちょっと印象に残ったのは、AWS(クラウドコンピューターサービス)について、「どの地域のデータセンターのコンピューターを使用しているのかは不可視化されている」という文面。この視点はなかったな、と思えるような新たな視点も多く、新鮮な部分もありました。そして、この本が出てから現在までのあいだでも、AIまわりは結構変化があったなぁ……ということを痛感しながら読みました。
途中で出てくる、お祖母様のぬいぐるみのエピソードには、思わず「著者自身はどうだったんだろうな」と思いを馳せてしまったりもしました。雨宮まみさんの時もそうでしたが、亡くなった著者が、生前のエッセイで誰かの葬儀について書いていると、思わずそんなことを考えてしまいます。
またこの本では、引用されている作品も気になるものが多かったです。
15位 すごすぎる天気の図鑑
双子のライオン堂で開催されているサイエンス読書会の課題図書になっていたので読みました。
14位 愛しのアラスカン・マラミュート
国会図書館で、電子化されたものを読みました。有名な「埼玉愛犬家殺人事件」の死刑囚の妻の本。著者は本当にアラスカンマラミュートが好きで、ドッグショーも楽しんでいるということが伝わってくる。「支えてくれる主人への感謝」のくだりは、「関根元のことだよね……」とフクザツな気持ちに。それにしても、犬カフェで見るアラスカンマラミュートと、この本の掲載写真の個体では、毛並みの雰囲気など少し違う気がして、流行りの傾向があるのかもしれないな、と思いました。
13位 妖怪がやってくる
12位 図解 コーヒー一年生
『図解 ワイン一年生』が良かったので同シリーズのこの本も買ってみた。監修者は違うものの、イラストや漫画は同じ人なので相変わらず分かりやすくかわいい。コーヒーの味には鈍感な私だったけど、この本を読み、以前いただきものとしてもらったコーヒー豆の産地を改めて見てみたり、楽しみが広がった気がする。数年前、コーヒーの飲み比べイベントに一度行ったことがあったけど、この本の内容を思い出しながら、また行ってみたい。
11位 男性の育児休業
20年前の本だけど、良くも悪くも現代でも通用する部分もあり、思っていたほど内容に古さは感じなかった。他国の事例も紹介されていて良き。「少子・高齢化」はこの頃はまだ少し他人事感を感じる。「ファミリー・フレンドリー施策」は初めて聞いたかも。中公新書って、いわゆる政治や歴史、理系の内容が多い印象が強かったけど、家族や性愛関係の本も意外とある上、データに基づいた議論が多くて面白い。読み込むのに少し時間はかかるけど。
10位 2050年再エネ9割の未来
9位 大地の五億年
8位 すごい哲学
7位 がん闘病日記
母が癌治療のために通う病院に置いてあり、通院のたびに少しずつ読み進めた。経済アナリストとしてだけでなく、さまざまな仕事をした人の、人生の集大成のエッセイとして面白かった。特に印象的だったのは、「お守りをくれる人は、健康食品を贈る人とは違い、純粋な善意だから嬉しい」ということ。そういう考え方もあるのか。B宝館の割引券や童話もついててお得な感じ。B宝館にも行ってみたい。陰謀論みたいなことを言うようになったのは、何が理由なんだろうな。
6位 ちいかわ お友だちとのつき合いかた
小学生向けの本だけど、コミュニケーションの本として勧める人が多く気になっていた。セールを機に購入。「こうしたほうがいい、これがベスト」という主張は最小限で、多様なコミュニケーションのやり方を受け入れたうえで「次は◯◯してみよう。」と提案するものが多く好感が持てる。終盤も「どのやり方がベストか」ではなく「ちいかわたちは、どうしたでしょう?」というクイズ形式にしているのが、過剰な意味づけを減らしていて良いと思った。陰口に関しては厳しい気がしたけど、SNSが一般的な時代を考えるとこのくらいでいいのかも。
5位 自閉症は津軽弁を話さない
4位 幸福の憲法学
3位 宇宙(そら)を編む
2位 「まさか」の人生